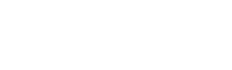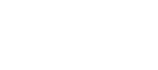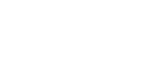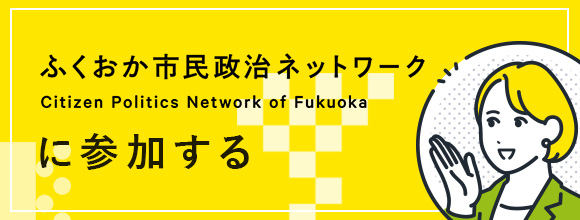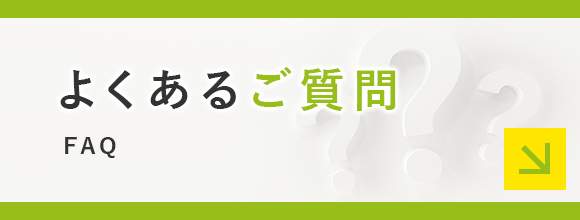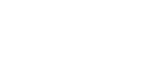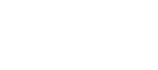参議院議員選挙にあたって 私たちが考える選択的夫婦別姓
選択的夫婦別姓について、運営委員会で改めて考えました。
自分たちも生活のなかで「姓」の問題について直面し、考えた経験があります。
・資格で働き続けるには、改姓が障害となった。
・自分の姓を大切にしたいので別姓で暮らす選択をしているが、子どもたちも理解し、とても素敵な家族を身近に知っている
・選挙のとき、候補者の旧姓しか知らない人には認知してもらえないのではないかと姓について考えた。 など…
私たちは自分を大切に生きるためにも、選択できる自由は重要だという思います。
多様性が言われ“個”を尊重する社会のはずなのに伝統的な家族観に縛られている感じがあるのは否めず、これを機会に社会が変わっていくことを期待しています。
選択的夫婦別姓の問題は、28年ぶりに審議入りしましたが、6月に継続審議とすることで与野党合意し、参議院選挙では大きな争点になっていません。
法務省の審議会が、選択的夫婦別姓にむけて民法改正の答申をまとめたのは1996年。実に30年経った現在も議論が進んでいません。
夫婦同氏制度が(旧)民法で定められたのは1898(明治31)年。
「家」制度を導入し、夫婦とも「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用し、夫の姓を名乗る形が一般的になったということです。そもそも「家制度」(家父長制)では、女性は結婚すると法的な行為能力が制限される「無能力者」とされ、働くためには夫の許可が必要であり、財産は夫が管理し、相続権・親権もないとされていました。
戦後の新民法では、どちらかの姓を選択できるようになりましたが、夫の姓を名乗ることが圧倒的に多いのが現状です。「家制度」もなくなりましたが、根深く染みついた意識が残っているのではないでしょうか。
世界を見渡しても、結婚後に夫婦同姓を法律で義務付けているのは日本のみということです。
皆さんへのアンケートでも、“いつまでこの問題を待たせるのか?”“これは女性の人権の問題で、実際に困っている女性がたくさん存在することをわかってほしい”“不利益を感じる人をなくしたい”“結婚することに弊害を感じない社会にしたい”などの声がありました。
新聞社の調査でも約7割の人が選択的夫婦別姓に賛成です。
選択できる自由は認めてほしいということではないでしょうか?
多様な家族のありかたを認めることこそ、人権を尊重する民主主義の国の姿だと思います。
共同代表 豆田優子
この記事を書いた人